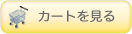チュダー王朝
チュダー王朝の料理
チュダー王朝

テューダー朝(テューダーちょう、英語:Tudor dynasty)は、イングランド王国(1485年 - 1603年)およびアイルランド王国(1541年 - 1603年)の王朝。チューダー朝とも。
テューダー家はウェールズを発祥とする、かつてのウェールズの君主の末裔の家系であったが、ヘンリー7世の祖父オウエン・テューダーはイングランド王ヘンリー5世の未亡人キャサリン・オブ・ヴァロワの納戸係秘書を務める下級貴族に過ぎなかった。
しかしオウエンはキャサリンと結婚し、その間に生まれたエドマンド・テューダーらの子供たちは一躍、ヘンリー6世の異父弟として、またフランス王家の血を引く者として上級貴族の一員となった。
エドマンドが、エドワード3世の四男ジョン・オブ・ゴーントの曾孫であるボーフォート家のマーガレット・ボーフォートと結婚し、その間に生まれたリッチモンド伯ヘンリー・テューダーは母方の血統により最後のランカスター家の王位継承権者となった。
1485年、ヘンリー・テューダーはボズワースの戦いでリチャード3世を破ってヘンリー7世として即位し、テューダー朝を開いた。
百年戦争、薔薇戦争で疲弊した諸侯を抑圧して絶対王政を推進し、海外進出にも積極的で、その政策はヘンリー8世、エドワード6世、メアリー1世、エリザベス1世に受け継がれ、テューダー朝の全盛期を築いた。エリザベス1世の死によりヘンリー8世の血筋が絶えたため、ヘンリー7世の血を引くスコットランド王ジェームズ6世がジェームズ1世としてイングランド王に迎えられ、イングランドにおけるステュアート朝を開いた。
王家の出自もあって、この時代に国王の臣下として活躍した人物には、フランシス・ドレークやウォルター・ローリーなどウェールズ系が多いと言われている。
(引用 ウィキペディア)
チュダー王朝の食卓

16世紀の英国の食生活は、ファッションほどの激変は見られなかった。
ただ新大陸から数種類の新しい食品や、フォークを使い始めた事などを
除けば、基本的に中世とあまり変わりがなかったのである。
小麦は豊富な肥料を必要とする。それゆえ純正な小麦から作ったパンを口に
できるのは、王侯貴族だけに限られていた。農民たちは、もっと手のかからない
ライ麦や大麦を育てて、自宅の食卓に乗せた。不作の年には、そこにドングリの
粉を混ぜて焼いたという。
もっとも貧しい小作農達の主食は黒くて重いライ麦パンか、「Carter's bread」
という、ライ麦と小麦の混合パンだった。独立自営農民(ヨーマン)は、それより
はましな全粒パン「yeoman's bread」を食した。
もっとも高価な白パン「marchet」は貴族だけが口にできるものだった。
中世からチューダー王朝にかけて変わったものといえば、料理を乗せる皿が
干からびたカチカチのパンの切れ端から、木の皿に変わった事だろう。
宮中では銀器や金の食器が使われた事は、いうまでもない。
料理はたいがい手でつまむものであり、食事中は体に触れることは不潔な
マナー違反だった。貴族であれば薔薇香水入りの水で、農民ならば普通の
水で手をすすいで、肉を摘んで食べた。もっとも、スプーンは昔から存在
していたので、ポタージュやスープを飲むのには困らなかったし、エリザベス
朝ではラフの流行により、首回りを汁で汚さないように、フォークが使われ
始めた。これはフランス王妃カトリーヌ・ド・メディチが、実家から持ち込んで
使い始めたものであった。
ロンドン南東チチェスター近郊、「国立野外博物館(World & DownLand
open air Museum)」では、チューダー王朝での調理を実演してくれる
という。チューダー風のボンネットとスカートエプロンをつけた女性が
16世紀そのままにの朝食を再現する。それによると、「夜明けに起きて
きた料理人は、まず火を起こして湯を沸かしながら、香辛料を挽く。」
全ての調理器具~バケツ・サイズの木製お玉、すりこぎ、ナイフ~などが
壁からぶら下がり、「meal ark」と呼ばれるタンスのような大型小麦粉収納用
の押入があった。食器洗剤の代わりに砕いた卵の殻で汚れ物を洗い、肉は暖炉
の煙で燻されながら天上から吊され、塩漬けの魚は干されて石のようにカチン
コチンだった。「国立野外博物館公式サイト」
香辛料は貴重品なので、棚に入れてカギをかけた。また、当時の主な飲料だった
エール(ビールの原型)や林檎酒もまた、キッチンで醸造された。
ポーツマスやサザンプトンの港の近かったチチェスターなどの海浜地帯では、
海産物も好まれた。塩タラやニシンの他に、淡水魚の鯉も食用だった。
また、意外なことに「牡蛎」は貧乏人が食べたという。
牡蛎は英国において、フランスほど珍重されなかったらしい。
16世紀、人々は明け方起き、6~7時の間に朝食をとった。農民はパンにエールのみ
か、オートミールの粥かポタージュを。王侯貴族は3皿のメインディッシュに白パン
を食した。昼は一日のうちで最も重要な食事、すなわちディナーである。
11~12時の間が昼食の時間だった。農民といえども、パンやオートミール粥の
他にチーズ、運が良ければ肉類も食卓に上がった。
夕方の6~7時の間が夕食(Supper)である。就寝前に胃に負担をかけぬように
農民は主に野菜のポタージュにパンをとった。王侯貴族はチョウザメや野鳥のパイ
などの珍味を肴にフランス産のワインを傾けた、という。
いわゆる「アフタヌーン・ティー」の習慣は、19世紀、ベッドフォード公妃が
始めたものだと伝えられている。
16世紀、野菜は生食されることは少なく、主にシチュー(ポタージュ)
にして調理された。玉葱、エンドウ豆、ほうれん草、カブ、ニラ、人参。
果物もまた種類が多く、林檎、プラム、西洋なし、イチゴ、サクランボ他、
各種の野生のベリー類(ブラックベリー、ラズベリー)も好まれた。
芽キャベツが記録に上ったのは、1587年が最初である。
主な蛋白源は鶏卵と乳製品、特にチーズだったが、ベーコンもまた最も手近な
蛋白源の1つであった。
豚は他の家畜に比べて雑食性が強く、放し飼いにしていると、勝手に
ドングリなどを食べて肥え太った。そして晩秋11月、長い冬の備蓄のために
豚を屠殺した。それぞれの部位が違う濃度の塩に漬け込まれて、ベーコン、ハム
ポークピクルとなり、断片は洗った腸に詰めてソーセージとなり、脂身はラード
に、血はオートミールに混ぜて固めたブラック・プティングになった。
野菜は香辛料と酢で漬け込まれ、果物は砂糖煮されてジャムとなり、冬の間の
食料となった。それは中世から16世紀を経て、19世紀初頭まで受け継がれた
伝統であった。
王侯貴族ともなると、牛豚羊以外に、スポーツハンティングでの獲物もよく食べた。
エリザベス1世も狩で、自ら矢を放ち、射止めたシカに止めを刺すことを好んだ。
シカに止めを刺すエリザベス(画像)/ブック・オブ・ハンティングより/大英博物館所蔵
シカや猪の他に、野鳥もまた好まれた食材であった。
ヘンリー8世、第3王妃のジェーン・シーモアは妊娠中の真冬に「ウズラ肉が食べたい」
と言い、季節はずれであるために、フランスから輸入したという。
クジャクはローマ時代から宴会料理の1つであったし、白鳥は七面鳥が普及するまで
クリスマスのご馳走であった。七面鳥が初めて英国に紹介されたのは、1519年だった。
(引用:「概説イギリス文化史」ミネルヴァ書房)